日本HPの“速くて安い”第2世代Core i7搭載ノートを徹底検証:新Core i7搭載で6万円台から(1/5 ページ)
新Core i7搭載で求めやすい価格帯の大画面ノートPC
1月11日、日本ヒューレット・パッカードの個人向けノートPC「HP Pavillion Notebook」シリーズから、2011年春モデルが発表された。先日の2011 International CESで発表されたばかりの第2世代Core iシリーズ(開発コード名:Sandy Bridge)を積極的に採用しつつ、低価格モデルも拡充することで、製品ラインアップを強化している。
ここではHP Pavillion Notebookの2011年春モデルから、第2世代Core iシリーズのCore i7を採用した17.3型ワイド液晶搭載ノート「HP Pavillion Notebook dv7-5000」を中心として、その弟分である15.6型ワイド液晶搭載ノート「HP Pavillion Notebook dv6-4000 Premium」も交えて、じっくり実力を見ていこう。これらは、最新アーキテクチャを盛り込んだうえでコストパフォーマンスにも注力した注目機種だ。
dv7-5000はオンラインストアのHP Directplusなどで取り扱う直販モデルのみ、dv6-4000 Premiumは量販店モデルと直販モデルが用意されるが、今回はハイスペックな構成で購入できる直販モデルを試した。
Huron Riverプラットフォームをいちはやく採用
dv7-5000とdv6-4000 Premiumにおける最大の特徴は、何といっても「Sandy Bridge」こと第2世代のモバイル向けCore iシリーズを採用していることだ。このモバイル向けの第2世代Core iシリーズと対応チップセット(開発コード名:Cougar Point)で構成される新プラットフォームは「Huron River」の開発コード名で呼ばれる。
すでにデスクトップ向けの第2世代Core iシリーズについては、PC USERでも解説記事やレビュー記事を掲載しているが、モバイル向けの第2世代Core iシリーズも基本的な構造や機能は共通だ。
最大の特徴は、CPUにGPUコアを内蔵しており、それを前提にキャッシュメモリやメモリコントローラを再設計していることにある。第1世代Core iシリーズのデュアルコアモデル(開発コード名:Arrandale)でもCPUにGPUを統合していたが、半導体チップ自体は別々であり、同一のCPUパッケージ内で2つのチップを結合したものだった。また、CPUコアは32ナノメートルプロセス、GPUコアは45ナノメートルプロセスと別々の製造プロセスルールを採用していた。
要するに不完全な統合だったといえるが、Sandy BridgeではArrandaleで別々だったCPUコアとGPUコアを1つの半導体チップ内に集積しており、CPUコアとGPUコアの32ナノメートルプロセス統一化、CPUコアとGPUコアでのキャッシュ共有やリングバスの採用によるI/O負荷の分散、さらにTurbo Boost Technologyの強化(Turbo Boost Technology 2.0)などによって、性能向上と消費電力低減の両方が期待できる。
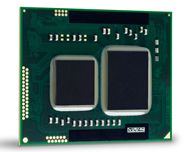
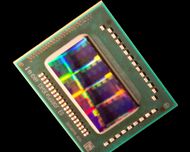 左が旧世代のCore iシリーズ(Arrandale)、右が新世代のCore iシリーズ(Sandy Bridge)。Sandy BridgeではArrandaleで別々だったCPUコアとGPUコアを1つの半導体チップ内に集積した
左が旧世代のCore iシリーズ(Arrandale)、右が新世代のCore iシリーズ(Sandy Bridge)。Sandy BridgeではArrandaleで別々だったCPUコアとGPUコアを1つの半導体チップ内に集積したまた、モバイル向け第2世代Core iシリーズに特有の機能としては、DisplayPort出力をチップセットを経由せず直接出力できる「eDP」(Enbedded DisplayPort)に対応する点が挙げられる。ArrandaleでもeDPをサポートしていたが、外部GPU接続用のPCI Expressと排他利用にとどまっていたのに対し、PCI Expressと独立して用意される点が異なる。
もっとも、現状のノートPCではチップセットを経由してのLVDSインタフェースによる液晶ディスプレイ出力が一般的なので、まだ実質的なメリットはない。将来的には消費電力と実装面積の面で、このeDPの存在が大きな意味を持つこともあるだろう。
CPUは第2世代Core i7から選択可能
では、dv7-5000の基本スペックを確認しよう。CPUの選択肢は、Core i7-2820QM(2.3GHz/最大3.4GHz/3次キャッシュ8Mバイト)、Core i7-2720QM(2.2GHz/最大3.3GHz/3次キャッシュ6Mバイト)、Core i7-2630(2.0GHz/最大2.9GHz/3次キャッシュ6Mバイト)の3種類が用意されている。いずれのCPUもクアッドコアで、TDP(熱設計電力)は45ワットだ。
この45ワットというTDPはCore i7-840QM(1.73GHz/最大3.06GHz/3次キャッシュ8Mバイト)やCore i7-740QM(1.73GHz/最大2.93GHz/3次キャッシュ6Mバイト)など、第1世代Core iシリーズのクアッドコアモデル(開発コード名:Clarksfield)と同じだが、これら第1世代のクアッドコアモデルがGPUコアを内蔵していなかったのに対し、第2世代ではGPUコアも含めてのTDPなので、GPUコアのぶんだけTDPが下がったといえる。
 CPU-Zによる情報表示画面。今回入手したdv7-5000の直販モデルは、Core i7-2820QMを搭載していた。このCPUの基本動作クロックは2.3GHzだが、アイドル時には省電力機能のEIST(Enhanced Intel Speedstep Technology)により動作クロックと電圧を下げる。アイドル時の動作クロックは800MHzだった
CPU-Zによる情報表示画面。今回入手したdv7-5000の直販モデルは、Core i7-2820QMを搭載していた。このCPUの基本動作クロックは2.3GHzだが、アイドル時には省電力機能のEIST(Enhanced Intel Speedstep Technology)により動作クロックと電圧を下げる。アイドル時の動作クロックは800MHzだった関連キーワード
Core iシリーズ | Core i7 | HP | ウーファー | ノートPC | Radeon | Sandy Bridge | SSD | DirectX 11 | Intel Turbo Boost | Arrandale | Intel HD Graphics | Huron River | クアッドコア | 2.1ch | Altec Lansing | Blu-rayドライブ | 直販限定モデル | HP ENVY
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
アクセストップ10
- もう全部、裏配線でいいんじゃない? 「ASUS BTF DESIGN」が示す自作PCの新しい形 (2024年04月19日)
- ノートPCに外付けキーボードを“載せて”使える「タイプスティックス/打ち箸」に新色 (2024年04月18日)
- さらなる高速化を実現! PCI Express 5.0接続SSDの新モデル「Crucial T705」を試して分かったこと (2024年04月18日)
- 話題になったトラックボール「IST」も登場! エレコムのPC周辺機器が最大21%お得に買える (2024年04月19日)
- Core Ultra搭載の「Let's note FV5」を徹底検証 プレミアムモバイルの実力は? (2024年04月19日)
- MSI、第12世代Core i3/i5を採用したミニデスクトップPC「Cubi 5」 (2024年04月19日)
- ついに8K対応した「Insta360 X4」の画質をX3と1インチ360度版で比較 今買うべき全天球カメラだと確信した (2024年04月16日)
- あなたのPCのWindows 10/11の「ライセンス」はどうなっている? 調べる方法をチェック! (2023年10月20日)
- バッファロー製Wi-Fiルーターに脆弱性 対象機種は今すぐファームウェア更新を (2024年04月17日)
- 東プレREALFORCEキーボードが10%オフ! ゲーミングキーボードも対象に (2024年04月18日)



